 |
||||||||||
| 
 早稲田大学GITS 早稲田大学GITS新入生懇親会 H20年9月22日、早稲田大学GITS新入生懇親会。東南アジアの留学生の皆さんと楽しく交流いたしました。 






都市問題会議in静岡  第69回全国都市問題会議がH19年10月11、12日の2日間静岡市で開催されました。全国の市長、市議会議員、随行職員等が参加します。今年は2千名余りの参加でした。本庄市からは吉田市長、正副議長含めて10名が参加しました。テーマは「分権時代の都市、ひとー地域力、市民力―」で基調講演と一般報告が行われました。徳川家康が大御所となって駿府に入城してから4百年ということで大会を盛り上げる色々なイベントが行われていました。正に地域力、市民力を発揮する場となっていました。 第69回全国都市問題会議がH19年10月11、12日の2日間静岡市で開催されました。全国の市長、市議会議員、随行職員等が参加します。今年は2千名余りの参加でした。本庄市からは吉田市長、正副議長含めて10名が参加しました。テーマは「分権時代の都市、ひとー地域力、市民力―」で基調講演と一般報告が行われました。徳川家康が大御所となって駿府に入城してから4百年ということで大会を盛り上げる色々なイベントが行われていました。正に地域力、市民力を発揮する場となっていました。
総務常任委員会視察 H19年10月2日〜4日まで総務常任委員会で東北方面に視察に行きました。視察先は岩手県一関市(自主防災リーダー育成事業について)同じく岩手県の滝沢村(行政経営理念の制定)福島県須賀川市(防災対策及び花いっぱい運動)の3か所です。視察に先立ち9月6日に本市の現状について、企画財政部の大墳部長、小林企画課長、又総務部の腰塚部長、内笹井まちづくり課長より説明を受けました。 一関市 一関市は地震については「日本海溝、千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の、推進地域に指定されたこと。又水害の常襲地でもあることから、防災意識は行政、市民共に高いと感じました。自主防災組織の組織結成率は約60%で、基本理念は自助(自分の命は自分で守る)共助(自分たちの地域は自分たちで守る)というもので、そこに行政の公助が加わる形です。行政は自主防災組織への支援も行っており、夏休みに行われる泊まりがけのサバイバルキャンプの開催などは他に見られない試みと思いました。ここまですれば、地域住民の防災意識、知識、連帯感も育つでしょう。 一関市の取り組みは、平成10年にも北上川の氾濫があったことなどでも分かるように、防災の必要性が非常に高い地域である故、といえるかと思います。本市では災害が少ないせいもあり、住民の防災意識もそれほど高いとは思われません。しかし児玉地域には、土砂崩れ危険個所などもあることから、地域によっては、自主防災の組織を立ち上げたリ、リーダー養成を行った方が良いと思いました。 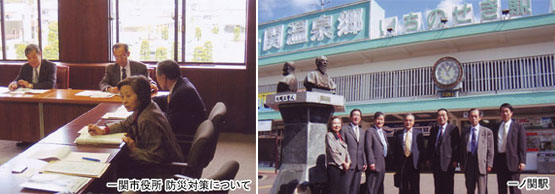
滝沢村  2日目は人口5万3千人余り「人口日本一の村」盛岡市に隣接する、滝沢村を視察しました。村ではありますが、その行政経営についてはマスコミにも取り上げられており全国的に高い評価を受けております。 2日目は人口5万3千人余り「人口日本一の村」盛岡市に隣接する、滝沢村を視察しました。村ではありますが、その行政経営についてはマスコミにも取り上げられており全国的に高い評価を受けております。
ここで新しい考えだと気付かされたのは、行政の使命は住民の「幸せ」を探求し、可能にすることにあるとした事です。私どもはともすれば「住民福祉の向上に努める。」という言い方をします。これは行政サービスを提供する上で普遍的価値と思いますが、施設が整い、福祉サービスが充実すれば、それで住民は幸せになれるのか、考えなければなりません。「幸せ」とは個々人が主観的に感じる事で、そこまで踏み込んで「幸せ地域社会の実現」を目指すとしたところは素晴らしい視点だと思いました。そこに行きつくために「行政は経営である」という基本認識にたって、行政主体から住民・コミュニティ主体という新しい自治への変革を推進するエンジンと位置付けています。 そのために徹底的な職員の意識改革に取り組みました。特にISO14001、9001認証取得により、経営品質向上プログラムによる評価を取り入れ行政に民間の行政経営理念を取り入れることにより、組織の活性化を図りました。その結果H17年には岩手県経営品質賞を受賞しています。 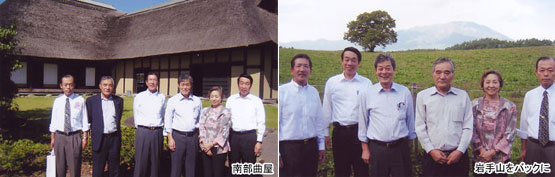 本市に於いても民間の手法を生かした行政経営が考えられても良いのかと思いました。
本市に於いても民間の手法を生かした行政経営が考えられても良いのかと思いました。
須賀川市  3日目は須賀川市の防災対策及び花いっぱい運動を視察しました。 3日目は須賀川市の防災対策及び花いっぱい運動を視察しました。
ここでは花いっぱい運動についてふれます。本市でも以前から花の植栽に取り組んできた団体がありJR本庄駅周辺、又小和瀬地区、久々宇地区、児玉駅周辺などでボランティア活動として、地域毎に特色ある活動をおこなってきました。18年度からは県費補助なども受けて、実行委員会形式で、花いっぱい運動がはじまりました。本庄、児玉地内合わせて10地域に広がっております。 須賀川では昭和61年から花いっぱいコンクールを実施し、個人や団体を表彰し、地域全体で花いっぱい運動推進に取り組んできました。19年度参加実績は団体一般の部―74、団体学校の部―30、個人の部―8、ふれあい花壇の部―8、と大変たくさんの応募があり、市民の関心のたかさが伺えます。余暇の増大と共に市民の、花に対する関心は高く、観光スポットにもなりえますので本庄市においても、この事業をうまく活用したいものです。 滋賀県視察  平成19年5月13日〜15日まで滋賀県方面に視察に参りました。その折、妹の嘉田滋賀県知事及び近江八幡の藤谷市長とも懇談致しました。又話題の、栗東新幹線駅予定地も見てきました。予定地は京都駅に近く、又隣接して大きな工場が有り、駅の片側は利用ができない状況です。在来線とのアクセスにも多大な経費を掛ける計画のようで、私どもの本庄早稲田駅に比べて合理性を欠いており、必要性は低いと感じたのは私ばかりでは無かったようです。
平成19年5月13日〜15日まで滋賀県方面に視察に参りました。その折、妹の嘉田滋賀県知事及び近江八幡の藤谷市長とも懇談致しました。又話題の、栗東新幹線駅予定地も見てきました。予定地は京都駅に近く、又隣接して大きな工場が有り、駅の片側は利用ができない状況です。在来線とのアクセスにも多大な経費を掛ける計画のようで、私どもの本庄早稲田駅に比べて合理性を欠いており、必要性は低いと感じたのは私ばかりでは無かったようです。

視察先は、嘉田もその立ち上げに中心的に関わった、地域の人々に大変人気の「琵琶湖博物館」、景観法に基づいた街づくりを積極的に進めている近江八幡市、集落営農を推進している東近江市の3か所です。 琵琶湖博物館 琵琶湖博物館は湖に張り出した烏丸半島にあり、大変景色の良いところです。博物館では学芸員の方より説明を受けた後、博物館内を案内して頂きました。琵琶湖の生い立ちや歴史、湖と人々の暮らしの展示や淡水魚の水族館もあり、子供たちにとっても楽しい空間となっていました。又古い民家も移築され、水道が引かれる前の生活の場が再現されており、昔の人々がいかに水と大切に関わってきたのか考えさせられました。 
近江八幡市 2日目は景観法に基づいた街づくりの先進地、近江八幡市を視察致しました。 近江八幡市は豊臣秀吉の甥、秀次が築いた城下町で近江商人発祥の地でもあり、古い歴史と文化を誇る街であります。秀次は城の外堀として両端を琵琶湖につないだ八幡濠を築造しそこに湖上を通行する商戦を引き入れ、経済の大動脈としました。歴史ある八幡濠も戦後の陸上交通の発展に伴い機能は失われ生活排水の流入と共にヘドロが堆積し、ゴミ捨て場と化しました。そこで40年代には埋め立てられる事となりましたが「堀は埋めた瞬間から後悔が始まる」のスローガンのもと市民が立ち上がり「保存修景運動」として全国でも例のない街づくり運動が始まったということです。その結果八幡濠は今では見事によみがえり人々の散策の場となっております。  八幡濠の修景運動の後、水郷の保全運動がおこり、景観法に基づく水郷風景計画を全国に先駈けて作り18年1月には、全国第一号の「重要文化的景観」(文化財保護法)に選定されました。和船に乗り水郷のヨシ原をめぐりましたが大変情緒あふれるものでした。又同年「美しいまちなみ大賞」(国土交通省)にも選ばれております。
八幡濠の修景運動の後、水郷の保全運動がおこり、景観法に基づく水郷風景計画を全国に先駈けて作り18年1月には、全国第一号の「重要文化的景観」(文化財保護法)に選定されました。和船に乗り水郷のヨシ原をめぐりましたが大変情緒あふれるものでした。又同年「美しいまちなみ大賞」(国土交通省)にも選ばれております。

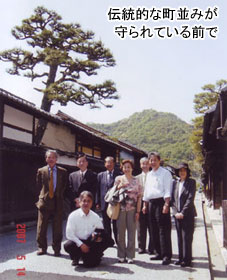 近江八幡で特筆すべき事は、まだ人々の景観に対する認識が薄かった時代に、すでに失われた景観は二度と戻らないという事に気付いていた事、そしてともすれば観光のために景観を守るという考えになりがちですが、景観は地域の自然、歴史文化を継承するため、そこに住んでいる人たちのためにあるという考えに基づいている事、又良好な風景の保全だけでなく、再生・創出を重視している事だと思います。観光に重点を置いていないとは言っても、平日にも関わらず町は大変賑わっていました。 近江八幡で特筆すべき事は、まだ人々の景観に対する認識が薄かった時代に、すでに失われた景観は二度と戻らないという事に気付いていた事、そしてともすれば観光のために景観を守るという考えになりがちですが、景観は地域の自然、歴史文化を継承するため、そこに住んでいる人たちのためにあるという考えに基づいている事、又良好な風景の保全だけでなく、再生・創出を重視している事だと思います。観光に重点を置いていないとは言っても、平日にも関わらず町は大変賑わっていました。
東近江市 3日目は東近江市の、集落営農を推進しております、柴原南あすなろファームを視察しました。ここは土地改良事業が完成した平成10年柴原南地区の農家42戸で柴原南あすなろファームを設立し、高齢化、担い手不足、儲からない農業に立ち向かい、徹底した支出削減に努め現在、厳しいながら黒字経営を続けているとの事です。ここの成功は、素晴らしいリーダーがいた事、そして水稲という作業が比較的単一化しやすい作物を作っている事にあるかと思います。本庄地域のような多種多様な作物を作る、近郊野菜地域では、どうだろうかと思いました。 
◎今回なぜ景観法の視察に行ったか◎ 本市においても新幹線新駅前の土地区画整理事業における新しい街の立ち上げにあたって、美しい町を立ち上げる事こそが、町のグレードを高め、新しい住人を呼び込める事になると考えたからです。 平成17年に国がなぜ景観法を制定したかというと、戦後日本は経済発展に邁進するあまり、乱開発による景観破壊が著しく、景観に対する配慮を欠いてきたという反省が出てきたからにほかなりません。景観法に基づく景観計画を作ることにより、色々な規制をかけられる事となります。個人の権限も守らなければなりませんが、私権の制限もしなければ美しい町は創出できるものではありません。「損して得取れ」の精神で、自分の好き勝手にできなくても、美しい町にすることが、町のにぎわいの基になるのでは無いでしょうか。新都心地区を雑多でとりとめの無い町にはしたくないものです。 | |||||||||